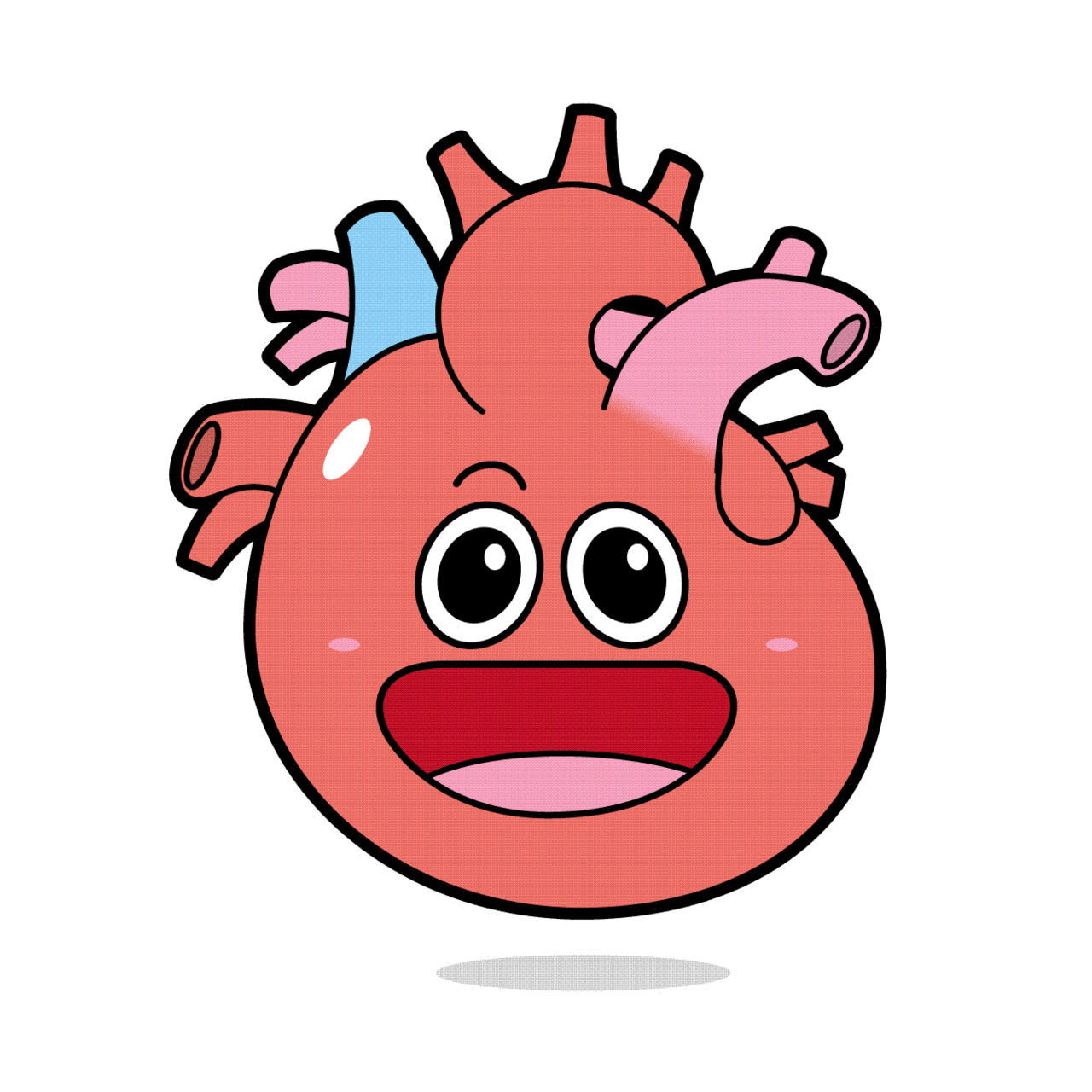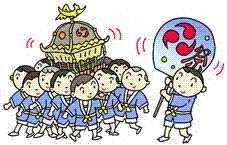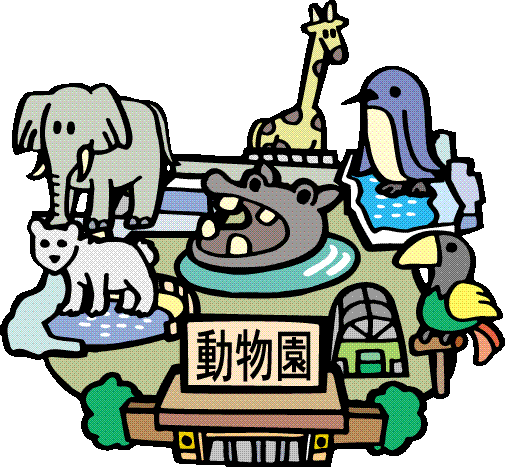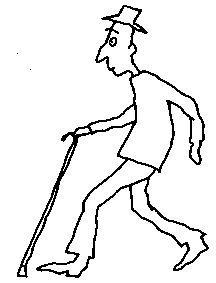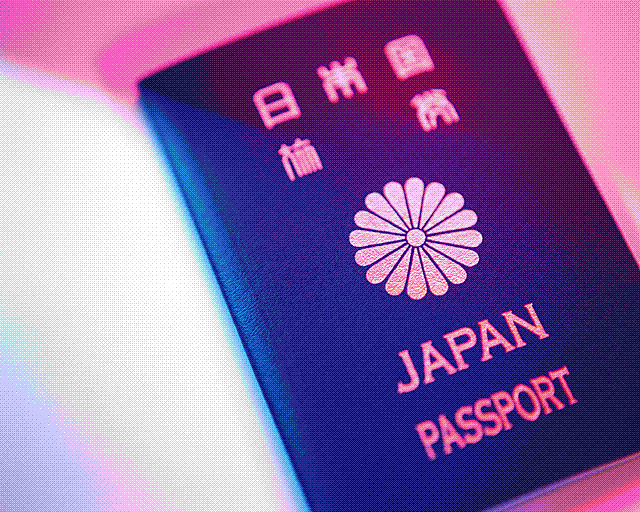| 1 | 戦争で生きる国づくり |
| 2 | 日本の宝 |
| 3 | プラトーンにはならない |
| 4 | 反原発ホラー |
| 5 | ノーベル賞はカンフル剤 |
| 6 | 平均寿命と健康寿命のはざま |
| 7 | ほんとに悲しい |
| 8 | みたび許すまじ |
| 9 | 「無縁社会」の中の新たな「縁」 |
| 10 | かけがえのない命のバトンが渡された |
| 11 | ふざけるな |
| 12 | 命のリレー |
| 13 | 今に来るぞ、日本国家の自己破産 |
| 14 | 家族のお楽しみ |
| 15 | 失ってはじめてわかること |
| 16 | 平和の民 |
| 17 | 平和憲法を瞳のように大切に |
| 18 | ようこそネットの世界へ |
| 19 | メルボルン事件に思う |
| 20 | 裁判官と国民の距離 |
たんぽぽ法律事務所
蒲公英 DANDELION 1990年7月2日設立
〒164-0011 東京都中野区中央3-39-1 たんぽぽ館1F
最寄り駅 地下鉄丸の内線「新中野」駅
受付時間:10:00 ~ 18:00
定休日:土日祝祭日 夏季休業 年末年始休業
戦争で生きる国づくり〜(2015年1月1日)元倉
国が武器輸出への資金援助検討開始

−師走の総選挙後テレビ朝日の報道番組でギョッ!
低利融資、輸出先への武器の訓練・保守修繕支援など、
日本の武器輸出企業へのバックアップだ。
これを報じた新聞がどうやら東京新聞だけ
−とのキャスターの話しにギョギョッ!
4月1日武器輸出原則解禁のニュースは、
マスコミ各社一斉に報道したのに、である。
日本の宝〜(2014年8月15日)元倉
プラトーンにはならない〜(2014年1月1日)元倉
四半世紀も前になる。
観終わったあともしばらく、
その映画の様々なシーンが頭にこびりついて離れなかった。
衝撃であった。
戦争はここまで人間を退廃、残虐・非道へ追い込むものか。
その映画、「プラトーン」(1986年)は、
初めて戦争の真実を描いた映画と高く評価され、
アカデミー賞作品賞・監督賞などを受賞した。
反原発いやがらせホラー〜(2013年8月15日)元倉
「反原発へのいやがらせの歴史展」に行ってきた。

8月10日午後のことである。
この日、観測史上6年ぶりに40度超えの地が出て、
東京都心でも37度にまでなったというが、
暑さにとても弱い私は息も絶え絶えに、
会場の新宿区区民ギャラリーにたどり着いた。
エアコンの涼しさを感じさせない盛況ぶりであった。
ノーベル賞受賞者は、多くの日本人にとって、
かなり昔から「天才」と同義である。
だが、「ただの」天才ではない。
「ただの」天才なら、日本人全体がここまで興奮しない。
日本人が興奮するのは、ノーベル賞受賞は、
「世界的」天才とのお墨付き、もっと厳密に言うと、
日本が「欧米列強」に負けない頭脳をもっていることの「証し」
と感じるからではなかろうか。
日本人の健康寿命は、
男性70.42歳、女性73.62歳であるらしい(2010年)。
「健康寿命」という言葉は、
多くの日本人にとって初耳だったのではなかろうか。
それもそのはず、
厚生労働省が初めて算出してこの6月公表したからである。
8月10日、
臓器提供の意思を書面に残さなかった脳死患者の臓器移植が、
その家族の承諾により実施された。
昨年2009年7月成立した改正移植法の施行から3週間あまり、
改正移植法に則った初めての臓器移植である。
臓器移植後進国日本における貴重な第一歩である。
こどもを怒るな、自分がこれまで通ってきた道やないか
年寄りを怒るな、自分がこれから通る道やないか
・・・90歳の伯父が聞かせてくれた言葉である。
だがしかし、思春期の子を持つ親にとっては、
この含蓄のある言葉もしばしば吹っ飛んでしまう。
人が借金をする理由は、様々である。
個人が借金する場合、
大抵は、身の丈に合わない買い物をする時である。
一般的に堅実な日本人は、借金を嫌う。
借金を嫌う日本人でも、やむを得ないかなと思える借金といえば、
住宅ローンとクレジットの買い物くらいだろう。
地価の高い日本でキャッシュでの住宅獲得は至難の業であるし、
クレジットは現金持ち歩きの不便を回避できる。
歩けない者の苦労と歩けることのありがたさ
が骨身にしみた昨年だった。
ある朝突然右脚に激痛が走った。
立っているだけでも苦しいが、脂汗流しながら歩いても数十メートルがやっと。
しゃがんだり座ると嘘のように症状は消失し、また少し歩ける。
診断名は「腰部脊柱管狭窄症」。 高齢者に多発する病気らしい。
60年前の今日。
すでに広島には原爆が投下されている。
明日長崎に再び原爆が投下されようとしていることを
日本国民はまだ知らない。
3月、息子が「おいら学校に行きたくない。」
とポツリとつぶやいた。
すわ一大事、我が家に登校拒否児童発生か?!
どうしたというのだ学校大好き少年。
と動揺する思いを押しとどめ、話しを聞いたところ、
毎日卒業式の練習で君が代を歌わされるのが嫌だという。
息子たち小学5年生は、在校生を代表し、6年生の卒業式に列席する。
10数年前、ワープロが流入した時、今より若かった私は、難なくその流れに乗れた。
が、パソコン、
ワープロソフトの方は難なくクリアしたが、
特にインターネット・メールの壁の前では、
長いこと呻吟した。
立派なデスクトップ型パソコン一式を買いそろえたのである。
仕事疲れをおして、夜の初心者教室に二度も通ったのである。
「猿にもわかるパソコン入門」などという指南書も読んだのである。
先達者達から話しも聞いたのである。
メルボルン事件の「受刑者」が仮釈放で帰国した。
事件直後の通訳を介しての取調べのビデオが
ニュースで流された。
「先進国」であり、
日本人観光客が大挙した訪れてきたオーストラリアにして、
こんな有様であったのか!
−日本人の多くがゾクッとしたのではなかろうか。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:10:00 ~ 18:00
定休日:土日祝祭日 夏季休業 年末年始休業
医療過誤事件、成年後見・財産管理などの高齢者問題、離婚・離縁などの夫婦(内縁)・親子の問題、DV、セクハラ、ストーカー、遺言書・遺産分割・遺留分侵害額請求などの相続問題、借地借家、不動産問題、マンション管理、建築紛争、交通事故、借金問題(任意整理・自己破産・個人再生)、刑事事件、労働事件、ホームロイヤー・・・専門家にご相談下さい。道が開かれます。
お気軽にお問合せください

お問合せ・相談予約は
<受付時間>
10:00 ~ 18:00
※土日祝祭日、夏季休業
年末年始休業は除く
たんぽぽ法律事務所
住所
164-0011
東京都中野区中央3-39-1 たんぽぽ館1F
アクセス
最寄り駅 地下鉄丸の内線
「新中野」駅
受付時間
10:00 ~ 18:00
定休日
土日祝祭日、夏季休業、
年末年始休業

![sgi01a201311261000[1]コブラ.jpg](/_p/acre/25944/images/pc/411b2a46.jpg)
![103[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/841216b8.gif)