後縦靱帯骨化症手術手技ミスで四肢麻痺に
〜2億3,500万円の損害賠償で償われるものは?
※名前、時期等、内容を損ねない程度に一部変えてあります。
1 明るい未来
「手術後回復室からご自分で歩いて病室に戻ることになります、
入院期間は1週間を予定しておいて下さい、
賢治さんは35歳と若いので骨化巣を早く取って楽にしてあげたい、
この手術で失敗したことはありません。」
−神手(かみのて)医師の説明に、
賢治さんは手術を受ける決心をした。
| ※ 後縦靱帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう) とは・・・ |
| 脊椎椎体の後縁を上下に連結し、脊柱を縦走する後縦靭帯が骨化し増大した結果、脊髄の入っている脊柱管が狭くなり、脊髄や脊髄から分枝する神経根が圧迫されて知覚障害や運動障害等の神経障害を引き起こす病気。 骨化する脊椎のレベルによってそれぞれ頚椎後縦靭帯骨化症、胸椎後縦靭骨化症、腰椎後縦靭帯骨化症と呼ばれる。 |
賢治さんの病は、「頸椎後縦靱帯骨化症」
・・・難病である。
いまだ原因は特定されていない。
多くの場合その進行速度は緩慢とされている。
賢治さんも、最初の症状である肩の痛みや手足の
軽いシビレを感じてから、すでに4年が過ぎていた。
その間徐々に、痛みの範囲が広がり、
手足に力が入らないことが時々出て来ていた。
とはいえ、勤務を休むこともなく、日常生活に支障もなかった。
一年前には瞳さんと結婚し、
ドライブやカラオケ、映画など二人きりの新婚生活を楽しんでいた。
あるとき、賢治さんは、書店で手にした一冊の本で、
2 手術
手術の日の朝、目が覚めたら元気な身体になれる
−賢治さんは希望にあふれていた。
頸椎(C3〜C5)に存在する骨化巣を摘出し、
前方除圧及びプレート・スクリュー等を用いた前方再建術による手術は、
予定通り約3時間で終了した。
しかし、賢治さんは歩いて病室に戻ることはできなかった。
意識不明、呼吸麻痺状態に陥ったまま救急救命センターに緊急搬送された。

意識を取り戻した賢治さんが自分の身体に起きた事態を認識していく過程は、
絶望への道であったことは想像に難くない。
過酷な介護の実態
リハビリ専門病院を経由して医療事故から1年後、自宅療養に入った。
賢治さんは、日常生活その他一切につき常時かつ全面的な介護を必要とする重症患者だ。
食事、ひげそり、洗顔、陰部洗浄、手足の洗浄、爪切り、耳かき、散髪、着替え、
移動介助、体交、可動域訓練、呼吸管理、体温管理、血圧管理、排泄管理等々。
賢治さんは一人っ子であり、70歳の父が郷里北海道にいるだけだ。
誰にも頼れない。
賢治さんの介護は全面的に一人瞳さんの肩にのしかかった。
中でも、呼吸管理、体温管理、血圧管理、排泄管理は、
賢治さんの生命維持にとって極めて重要な介護だ。
同時に介護者にとっては極めて過酷な介護だ。
<呼吸管理>
陽圧人工呼吸にて呼吸を維持している賢治さんの呼吸管理は、
ひとたびトラブルが発生すると生命に危険が及ぶため、
24時間態勢での注意と対処が必要だ。
常時サチュレーションモニターでSpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)のチェックが必要であり、
SpO2が下がりだしたら迅速に呼吸器を調整してSpO2を戻さなければならない。
アラーム音が鳴れば、夜中でも瞳さんは飛び起きて即座に対処する。
就寝後にSpO2が下がりがちなため、賢治さんの就寝後も一定時間モニターを監視する。
瞳さんの就寝は毎日午前2時半頃だ。

食事介助の際の呼吸管理は細心の注意が必要だ。
マウスピースを外している間は呼吸は停止している。
マウスピースを外す食事には、細心の注意を要する。
モニターでSpO2をチェックしながら、
マウスピースを外して食物を口に入れ、
口腔内に食物が残っていないことを確認してから
マウスピースを戻さなければならない。
口腔内に食物が残った状態でマウスピースを入れると、
誤嚥や窒息につながるからだ。
口に入れる食物の量にも注意が必要となる。
マウスピースを外している間はSpO2が下がり続けるので、
咀嚼・嚥下に時間を要すると、最悪の場合、
口に食物が残った状態で意識喪失につながりかねないからだ。
万一誤嚥しそうになった時には、素早い適切な対処も必要だ。
痰が気道に詰まると、窒息し、最悪の場合死に至る危険がある。
そのため、出てきた痰をこまめに取るだけでなく、
予防措置として胸を押して痰を押し出す排痰処置が必要となる。
また痰の出をよくするために、一日1〜1.5Lの水分補給は欠かせない。
<体温管理>
自律神経機能障害のため賢治さんの体温は、
冬には32℃台まで下降したり夏には38℃台まで上昇するなど
周囲の気温に影響を受け易いだけでなく、
例えば体温は36℃なのに本人は38℃の高熱と感じるなど、
本人の客観的体温と感覚が齟齬すること(異常感覚)がしばしばあり、
どう対処すべきかしばしば困難を伴う。
一日数回の検温、エアコンの温度・風量の調整、寝具の調整のほか、
マッサージ等の対処も必要だ。
夜間賢治さんが体温の異常感覚により目を覚ますことがあり、
その対処で瞳さんの睡眠は中断される。
<血圧管理>
自律神経機能障害のため賢治さんの血圧は変動が激しく、
収縮期血圧は80〜110mmHgを、
拡張期血圧は60〜80mmHgを、
それぞれ上下して安定しない。
また起立性低血圧を起こし、意識消失することもしばしばあるため、
適宜の血圧測定や表情・顔色・目の動き等に対する不断の注意が必要だ。
<排泄管理>
直腸膀胱障害(便秘・神経因性膀胱)により、
排尿は、尿道からカテーテルを挿入して排尿させ
膀胱を空にする(間欠導尿)必要があり、
排便は、肛門から座薬を挿入し一定時間経過後
手を使って便を掻き出す(摘便)必要がある。
導尿は、一日4回、各1時間前後を要し、
便処置は、週3回、各2時間前後を要する。
また、日中・夜間を問わず、
おむつから尿や便が漏れて衣類・寝具を汚すことがある。
そうなると着替え、衣類・シーツの交換に30〜40分時間を要する。
下痢症状に見舞われると、一日2〜3回便処置に時間がかかる。
賢治さんがデイケアに出かける週2回各2時間の間も、
瞳さんに、自分の身体を休める暇はない。
買い物・掃除・洗濯等の家事を集中的に行い、
時間があれば瞳さん自身の入浴もこの時間帯に手早くシャワーで済ませる
(瞳さんは自宅介護が始まって以来、一度も湯船につかったことがない。)。
買い物は賢治さんのそばを離れるため、
また瞳さんの入浴は賢治さんに呼吸トラブルが発生した時対応が遅れるため、
賢治さんの在宅中を避ける必要があるのだ。
瞳さんは、午前7時頃より午前2時半頃までの約19時間介護に拘束され、
睡眠時間は夕方約30分の仮眠を含めたとしても一日5〜6時間だ。
しかし、この短い睡眠時間も、モニターのアラーム音が鳴り出したり、
体温の異常感覚により賢治さんが起きたり、
便漏れ・尿漏れがあったりすると、中断する。
かような介護生活の中では、瞳さん自身の生活は無いに等しい。
着飾って出かけることも、買い物を楽しむことも、
自分の趣味を持つこともできないだけでなく、
人間にとって最低限度の生活の安らぎである睡眠・入浴も、ゆっくりできず、
食事も、自分用の普通食を作る時間はないので、
賢治さんの食事介助をしながら同じ食事をとる。
4 法的解決
初めて瞳さんが相談に来所したのは、医療事故から1ヶ月半たった、
まだ賢治さんの容体は不安定で、
気管切開下人工呼吸器を装着されている時期であった。
元の身体に戻るのか、
後遺症が遺るのか、残るとしてもどのような後遺症が遺るのか
−少なくとも瞳さんには、全くわからない、
しかし元の身体に戻る希望をなお失っていない時期だった。
カルテの証拠保全を含む調査を受任した。
約1年後神手医師の勤務する相手方医療機関との交渉を開始した。
1年以上にわたる交渉によって、相手方医療機関は、
頸髄損傷が神手医師の手術中の手技ミスによることを認めるに至ったが、
損害賠償額で請求と回答の間に1億円もの大きな開きが残った。
やむを得ず、裁判を提起した。
損害額、主として「介護費」の評価を巡って争われたが、
最終的に2億3、500万円の和解金で解決した。
裁判で請求した実損額の85%であり、勝訴的和解だ。
医療事故発生より3年が経過していた。
5 被害者と償い
本件医療事故の被害者は二人いる。
一人はもちろん、患者本人の賢治さんだ。
意識はしっかりしていながら、自分の身体は自分の意思のままにならず、
しかも新妻にその全てを委ねなければならない
−賢治さんの苦痛は、想像を絶している。
二人目の被害者は、妻の瞳さんだ。
30歳の若さで、あまりにあまりに重い介護の人生を歩むことになった。
本件の賠償金は確かに高額だ。
しかし、二人の現実の人生を思うとき、失われたもののあまりの大きさを思うとき、
その償いにはなり得ない。
せめても救いは、
妻は夫への変わらぬ献身と愛情を注ぎ、
夫は妻への深い感謝と愛情でこたえ続け、
二人が手と手を携えてこの苦難多き人生を力強く乗り越え始めたことだ。



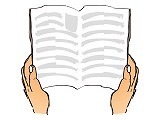


![4_05[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/2c9670e0.gif)
![6_04[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/318881b0.gif)
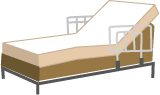

![taion2[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/7d2301b8.gif)
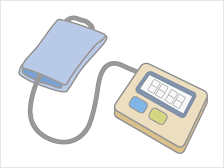
![6_02[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/fec6b69d.gif)

![8_15[1].gif](/_p/acre/25944/images/pc/d888a4f7.gif)

