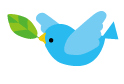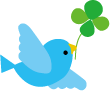1 高校生の頃、山道を歩いていて、
道沿いの渓流をツィーという鳴き声とともに、
コバルトブルーの小飛行体(翡翠色のカワセミ)が
あっという間もなく通過していく様を
はじめて見たときの感動は忘れがたいものがある。
都会から一時姿を消していたこのカワセミも、
最近は都心の公園や川(善福寺川、多摩川等)
でも見られるようになり、都会にもカワセミが戻ってきた。
渓流沿いの木立の上で、
ピーリーリー、ピールリピールリ、ジッジッなどと
美しい声でさえずるオオルリ(♂)をはじめて見たのは、
日光の神橋近くのことであった。
頭部から背、尾の先まで光沢のある青色に輝く美形であった。
昔、富士山5合目でみたルリビタキ(♂)も、
そのさえずりは、ヒッキョロキョロキョロリなどと魅力的。
頭部から背中、翼、尾羽まで、
その上面は明るい青色で覆われているが、
脇はオレンジ色というアクセントのあるきれいな鳥である。
戸隠高原の森林公園で出会った、
オオルリよりは小柄なコルリ(♂)は、
高木の梢でチッチッチッ、ピンツルルチッカララララ
と美しい声でさえずっていた。
その後、清里高原では、
森林の中の草の茂みをホッピングをするように移動しながら
小虫を採餌するコルリ(♂)に出会った。
上面は頭から、翼、尾まで暗青色、
対照的に下面は白色というすっきりした配色で、
端正できりりとした印象が残っている。
2 昨年は、「青い鳥」に都心の公園などで出会った。
上述のカワセミ、オオルリ、ルリビタキ、コルリなどが、
関東近辺で見ることができる「青い鳥」の代表格で、
バードウォッチャーあこがれの鳥である。
以前は、富士山5合目、富士山麓、山中湖周辺、日光、戸隠高原などの
有名探鳥地にその姿を求めたこれらのオオルリ、ルリビタキ、コルリなども、
春秋の渡りのシーズンには、都市部の公園でも、
休息場所、採餌場所となる樹木が生い茂る等の条件のあるところでは、
注意して探すと目にすることができる。
公園散策の楽しみも増すというところか。
3 青い部分の目立つ鳥といえば、
海辺の岩場で目にするイソヒヨドリ(♂)も、
頭・胸・背・腰は青藍色で脇にも青い羽毛のある美しい鳥で、
ホィッピーツィー、ツツヒーコーヒーなどという澄んだいい声でのさえずりも魅力的である。
2012年8月のたんぽぽニュース夏号(第35号)の表紙を飾ったサンコウチョウも、
嘴と目の周りのリングが鮮やかなコバルトブルーで青い部分が目立つ可愛い鳥である。
雄の尾は長く、頭から胴体部分の長さの2倍以上にも及び、
林のなかをひらひらと尾をなびかせて飛び、
採餌する姿は優美である。
そのさえずりは、ツキヒーホシホイホイホイホイ…と美しく、
この鳥もバードウォッチャーあこがれの鳥である。
さえずりが月(ツキ)日(ヒ)星(ホシ)と聞こえることから
三光鳥(サンコウチョウ)と名付けられたという。
4 奄美大島方面でしか見られれぬ瑠璃色のカラス科の鳥、ルリカケスも、
機会があれば出会いたい「青い鳥」である。
ギューイギューイケッケッ、グェィーグェィーと
うるさく飛びながら鳴くオナガも、
都会でも見られ、
声は悪いが翼と尾羽が薄い青色のきれいな鳥である。
ルリカケスの仲間で本土の平地の林でも秋冬には見られるカケスも、
ゲェーィ、ギャーギャーとうるさく鳴くが、
翼の一部(翼をたたんだ状態での体側部分)に白色、黒色、青色の美しい縞模様があり、
小さいが青色が美しく目立つ鳥である。
カケスやオナガの声の悪さは、カラスの仲間と聞けばそれも納得で、
その美しさに免じて我慢、我慢というところか。
5 「青い鳥」といえば、
幼い頃に読んだメーテルリンクの本を思い出す。
チルチル、ミチルの兄妹が幸福を招く「青い鳥」を求めて
旅に出て苦労する話といえば、
どなたも思い当たるであろう。
バードウォッチャーの求める「青い鳥」も、いつも簡単に見られるとは限らない。
会えると思って出かけても会えないことも多い。
それだけに、散歩中や旅先などで、思わぬ時に「青い鳥」に出会えば、その喜びは倍増する。
あらかじめ情報を集めるなど準備を整え、苦労して遠い道のりを出かけ辿り着いたところで、
予想どおりに出会えれば、さらにその喜びは大きい。
現実社会に目を向けると、昨今の不況下での就職難や格差社会の厳しい現実がある。
不況脱却・格差社会是正には「政治」に期待するところが大であるが、
思うように進まない現実がある。
他方、現在の職場に不満を感じ、
「もっと自分に適したいい職場があるに違いない」
「自分の能力を生かせる仕事があるはず」などと
「理想の職場」を求めて転職を繰り返したり、
職に就かないという思考パターンの若者が増えているという
(「青い鳥症候群(青い鳥シンドローム)」)。
五木寛之氏は、「青い鳥のゆくえ」(角川文庫)で、
安易に手に入る「青い鳥」(幸福、希望)はこの世にはいない、
自ら作り出すものとのメッセージを発している。
この五木氏のメッセージの解釈にはいろいろあろうかと思うが、
私なりに、矛盾多きこの現実社会の渦中で、自ら、
「青い鳥」を獲得するために努力すること、
人と人とのつながり・連帯を求め、闘いの中に身を置き努力すること
の大切さをあらためて感じつつ、
2013年の新年を迎えた。
![bn281-3[1].jpg](/_p/acre/25944/images/pc/11a45823.jpg)