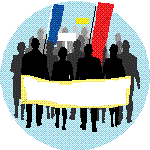「決める政治」「決断する政治」の行き着く先
消費税増税、原発再稼働論議等に思う
1 消費税増税法が、民主・自民・公明三党の談合のもと、
逆進性を拡大する、中小企業が価格に転嫁できない、
不景気での増税強行は日本経済をより沈滞化させる
等々の批判の声にまともに答えないままである。
野田首相と早期解散を確約させたい自民党谷垣総裁との密室談合では、
消費税増税法成立と引き換えに「近いうち解散」を約束したと言われる。
しかし、増税法成立するやいなや、予想されたこととはいえ、
早速、「近いうち」の解釈を巡り、民主・自民両党の思惑の相違が表面化。
いずれにしても、
2014年4月の消費税8%への引き上げ実施までには、
衆議院も参議院も選挙がある。
多数の反対世論が結集し、
庶民増税反対の声を国会に届けることで、
消費税増税談合勢力に厳しい審判を下し、
増税法廃止のレールを引きたいもの。
2 この間、マスメディアは、「決められない政治」を批判し、
消費税増税法に「政治生命をかける」という野田首相を後押した。
しかし、「決められない政治」には、それ相応の理由がある。
反対の世論が大きくなり、
多数の反対意見を無視することができないからこそ、
簡単には「決められない」のである。

反対世論のほか、与党内にも反対勢力を抱え、国論を二分するような問題
−今回の消費税問題のほかにも、
原発再稼動、普天間基地の辺野古への県内移設、
オスプレイ配備、TPP(環太平洋連携協定)への参加、
衆議院比例定数の削減等々−は、政府・首相の意向と言っても、
強力な反対意見を踏みにじって何もかも決める(強行する)わけにはいかない。
国民多数の願いを反映し、大義ある反対意見、少数意見もあるのである。
合理的理由に基づく大義ある反対意見は強い。
為政者は、かかる反対意見に謙虚に耳を傾けねば、
自らの政権基盤をも揺るがすことになりかねない。
だからこそ、簡単には、「決められなかった」のである。
しかし、かかる大義ある反対意見を無視して、
「決められる政治」をあおり、賛美し、
一方の意見に肩入れするマスメディアの論調は、
強者の「決断」「独断」(独裁につながりかねないであろう。)
を助長するものであって、異様としか言いようがない。
かかるマスメディアの現状は、