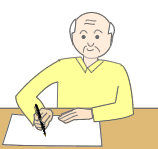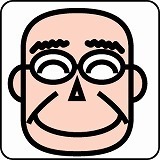| 遺言書 ○○○・・・ ×××・・・ 2012年1月1日 |
老い支度を考える時、
自分が墓場の陰に身を隠したその後、
相続人間に無用なトラブルを起こさないために、
ささやかな自分の財産の行く末を決めておきたい
・・・そう思うのは人情である。
よくよく考えてしたためた遺言書。
これは、遺言書の文言をめぐって、
相続人間ではなく、遺言者は予想もしなかっただろう、
銀行との間でトラブルが発生したケースである。
【 ケース1 】 自筆遺言書の文言めぐり訴訟に発展。
自筆遺言書は、安価・容易さが長所である。
が、破棄・隠匿、不明瞭な表現などで、無効又はトラブルにもなる。
これは、公正証書遺言書ならトラブル回避可能と思われるケース。
妻を亡くした後の一人暮らしを心配した娘花子夫婦に請われ、
娘夫婦宅に身を寄せた茂雄さん、
感謝の気持ちとして、娘に自分の全財産をやり、
放蕩息子太郎にはビタ一文渡すまいと、
「私は、動産・不動産.全て花子に遺贈する。」
・・・一行だけの遺言書を、達筆な筆でしたためた。
このシンプルな遺言書に、X銀行が預貯金の相続手続を拒絶した。
「全て」とは動産・不動産の全てであり、
預貯金を含まないと言うのである。
遺言書によらず通常の手続で相続手続をするよう求めた。
通常の手続には、相続人全員の署名・捺印が必要である。
太郎は、すでに遺留分をはるかに超える請求をしていた。
すんなり協力するわけがない。
| 訴訟告知とは・・・ |
| その訴訟に利害関係のある第三者に訴訟を通知すること。 |
| 補助参加とは・・ |
| 利害関係のある第三者が、自己の利益を守るために、他人間の訴訟に参加すること。 |
花子さんはやむなく、
X銀行を相手に遺言書に従って預貯金を払い戻せと、
訴訟を提起した。
X銀行は、放蕩息子太郎に訴訟告知をし、
太郎も訴訟に補助参加してきた。
「全て」の文言と「動産・不動産」との間は、「.」で区別して
記載されており(いわば「.」は読点「、」の代わりである。)、
「動産・不動産」は単なる例示にすぎず、
従って、「全て」とは預貯金その他を含む遺産全てである。
また、他の銀行・証券会社では遺言書通りの相続手続を終了したが、
これはこの解釈が合理的であることの証左である。
裁判所は、こちらのこの主張を全面的に容れ、
本件遺言書は、預貯金を含めて全ての遺産を花子に遺贈する
としたものであることを前提に、預貯金全額支払いの和解で解決した。
なお、太郎は、全遺産が花子に遺贈されたことを前提として
すでに遺留分減殺請求をしていたので、
いまさら遺言書の文言解釈など争える立場ではなかった。
太郎は、この訴訟参加のために弁護士を依頼したのだが、
その後その弁護士の説得により適切な遺留分で納得して、
本件は遺言書全般の解決をみた。
【 ケース2 】 公正証書遺言書の文言めぐり訴訟前に解決。
公正証書遺言書は、費用と準備がかかるのが短所であろう。
が、遺言書は公証役場に半永久的に保管され、
公証人によるチェックで後日のトラブルを回避できるなど、
自筆遺言書では得られない安心・安全がある。
しかし、複雑・長文な内容となると、公証人のチェックにも限界がある。
これは、公正証書遺言書でも複雑な内容の場合は、
専門家に案文を依頼すべきと思われるケースである。
勝夫にだけは遺産を渡したくない、と遺言書を書いた。
様々な思いをこめて、多数の遺産についてこと細かく指示し、
その結果遺言書は複雑・長文になった。
栄介さんは、一定の法律知識があったので遺言書の案文は自力で作成したが、
慎重を期して自筆遺言書ではなく公正証書遺言書にした。
この複雑・長文の遺言書に、Y銀行が貸金庫の開扉手続を拒絶した。
遺言書の「不動産及び遺言者の有する預貯金等を相続させる。」
との一文について、

「預貯金等」の「等」は、預貯金と同列のものを言い、
貸金庫契約上の権利・義務を含まないと言うのである。
遺言書によらず通常の手続で相続手続をするよう求めた。
通常の手続には、相続人全員の署名・捺印が必要である。
兄弟姉妹に遺留分減殺請求権がないことを知っている勝夫は、
この遺言書を認めようとせず、法定相続分を請求していた。
すんなり協力するわけがない。
頭の固い銀行は、いったん言い出したら引かない。
しかし、訴訟は避けたい。
訴訟告知を受けて遺言書に不満な勝夫が補助参加してきたら、
余計にもめて時間がかかるであろう。
関係者の事情聴取と関係資料の探索の中で、

15年前遺言書作成の直後、
栄介さんが兄宛てに出した手紙が出てきた。
手紙には、近況報告のほか、遺言書作成に触れ、
公証役場に行けば遺言書が手に入ること、
遺言書を持っていけば「銀行は貸金庫を開けてくれるので」、
その中の財産を勝夫以外の兄姉で分けるよう書かれていた。
遺言書の解釈は、文言を形式的に判断するだけでなく、
遺言書全体から、また遺言書外の事情も勘案して、
遺言者の真意を探求すべきとするのが最高裁判例の立場である。
栄介さんの手紙と最高裁判例を添付し、
他行は本遺言書に従って貸金庫の開扉手続を終了したことも付言して、
遺言者栄介氏の真意は、
「預貯金等」に本件貸金庫契約の権利・義務を当然含むものである、
従って貸金庫を速やかに開扉するよう、Y銀行に迫った。
Y銀行は、約一ヶ月の検討の後、開扉手続に応じた。
訴訟は回避できた。やれやれである。
ちなみに、勝夫は、遺留分減殺請求権もない立場では戦うすべもなく、
その後、自分を排除して栄介さんの葬儀を行ったことなどの理由で
むりやり慰謝料を請求して、姉兄相手に、調停を申し立てた。
姉兄は、欲深いとはいえそこまでする弟を不憫にも思い、
また、紛争が長引くのは栄介さんの本意ではなかろうと、
100万円を渡して、本件遺言書全般の紛争を終結させた。