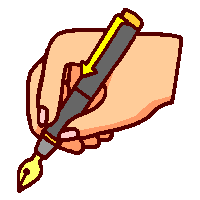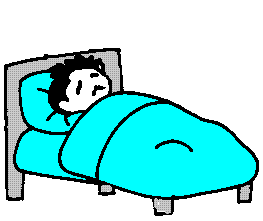1 幼稚園に元気に通園する5歳の女児。
ただ、繰り返し扁桃腺を腫らして高熱を出すので、
2010年8月、
市内の総合病院で扁桃腺の除去手術を受けることになった。
予定された扁桃摘出術の内容やリスク等については、
事前に外来診療時に、その手術が必要であること、
全身麻酔で行う必要があるが、
当日の夜か手術翌日には飲食が可能になり、
術後1週間で退院できること等を含め、
特別に困難な手術ではないという趣旨の説明を受けている。
2 手術当日
担当麻酔医は、血圧をモニターで確認しながら、
患児に、点滴による麻酔(全身麻酔)を開始。
その過程で、確実な気道確保のために
気管内チューブの挿入(気管挿管)が行われたが、
その措置が適切に為されなかったために、
患児の肺に十分には酸素が送られない状態になった。
耳鼻咽頭科の担当医が患児にメスを入れた後に、
急に血圧が低下し、患児は、予期されざる心肺停止状態となった。
担当医ら手術スタッフは、
不測の事態に驚愕し、パニック状態に至ったが、
しばらくして心臓マッサージ等の蘇生措置
及び挿管のやり直しがおこなわれた。
3 しかし、患児には、心肺停止状態が続いた結果、
低酸素性脳症となり、重度の脳障害(脳性麻痺)が残った。
患児が低酸素性脳症となったのは、
病院側の以下の過失によるものと想定できた。
① 担当麻酔医には、確実な気道確保のために
気管内チューブの挿入(気管挿管)を適切且つ確実に行うべき注意義務
があったにもかかわらず、当該担当医がこれを怠った過失
② 手術担当医らすべての手術スタッフには、
麻酔中に適切な気道確保が行われ、
患者(患児)に酸素が十分に送られるよう管理・確認すべき注意義務
があるにもかかわらず、これを怠った過失
4 病院側は、
本件医療事故の原因及びその法的責任について、
当初、曖昧な対応に終始した。
患児の両親は、
被害の大きさと不誠実な病院側の対応に不満を覚え、
法律相談に来所された。
相談の結果、
両親は、真相を究明し、被害回復及び再発防止を図るべく、
本件医療事故について、
証拠保全手続きによるカルテ類の保全を含む調査
を依頼することになった。
① 裁判所を介する証拠保全では、
いきなり裁判所の証拠保全決定書が病院に届けられ、
通常その1時間後に、 裁判所とともに、
弁護士は専門のカメラマンを連れて病院に赴き、
カルテ類の検証手続(全てを写真撮影する)をするので、
その時点でのカルテ類をあるがままの状態で入手し得る。
それだけ、病院側によるカルテ類の改竄(書き換え)
・隠匿(抜き取り)等を防ぎ得る可能性が高い。
② カルテ開示の場合は、
開示申請からカルテ入手までに数週間を要するのが一般であり、
その間に、病院側によるカルテの選定・改竄・隠匿等
の可能性を排除できないリスクがある。
費用の点では、カルテ開示に比べ証拠保全手続の方が、
弁護士費用や専門のカメラマンの費用などで高くなるが、
私どもは、一般にカルテ改竄のリスクを考え、
証拠保全手続を優先的にお勧めしている。
本件でも、両親は証拠保全手続を希望されたので、
裁判所に証拠保全を申し立てた。
その年の年末ぎりぎりに、裁判所による証拠保全が行われ、
本年1月には、カルテを入手した。
6 入手カルテの検討の結果、
病院側の麻酔に関し過失
(麻酔時に挿管チューブの先端が正しく気管内に挿入されなかった手技ミス
と担当麻酔医らがそれに気づくのに遅れを来たした過失)
が認められるうえ、
その過失と被害(患児の重度の脳障害)との間に
因果関係も認められると考えられた。
そこで、
本年4月にカルテ類の検討の結果を踏まえた「質問書」を
病院側に送った。
6月には、病院側の弁護士から、
本件手術時の麻酔措置に過失があること
その過失と患児の脳障害との間に因果関係があることを認め、
病院側の法的責任を肯定するとともに、
当方の要求に応え、
再発防止措置に努めていることにも触れる回答が届くに至った。
7 自分の足で元気に遊び回っていた患児は、
自ら歩きまわることはもちろん、
支えなしには立ち上がることさえもできないし、
食いしん坊であった患児は、
他の家族との食事の輪にも加われない。
鼻から胃に繋がれたチューブからミルク等流動食の補給を受けるしか、
自らの生命を支える栄養をも摂取できない。
また、重度の脳障害のために、
口鼻から自力で完全には呼吸できず、気管切開したままの状態が続いている。
しかし、患児は、現在、重度の脳障害を抱えたまま退院し、
病院への通院と県立療育園に通所しながら、
両親による自宅介護を受けている。
病状には未だ流動的なところもあり、
両親は、主治医・看護師・保育士等の指導・協力の下で、
在宅生活により、患児の治療・リハビリ等に全力を傾注しているが、
まだ症状固定との診断は下っていない。
その意味で、本件の全面的解決には、
未だ時間を要すると思われるが、
法的責任を肯定した病院側に対し、
損害賠償金中の内金として、
患児の治療・リハビリ等のために生じた既に確定済みの損害につき、
その支払いを請求したところである。
8 今、両親は、証拠保全手続の成功を喜びつつも、
何よりも患児の少しでも前に進む回復とリハビリのために
やれることは何でもするとの思いで、
涙をこらえ奮闘中である。
なお、両親は、将来、患児の症状が固定して全面解決に至る際には、
本件医療事故に直接の責任を負うべき麻酔医らに加え、
院長はじめ管理責任者らの関係者から、
本件医療事故の責任を認めた上での誠意ある直接の謝罪を受けることを強く求め、
病院側にその思いを伝えている。
患児の回復・成長とリハビリの前進を祈るや切である。