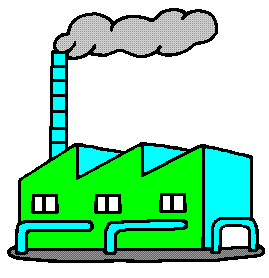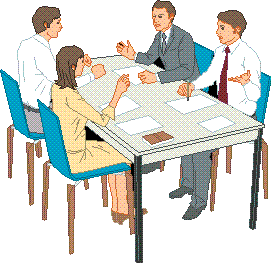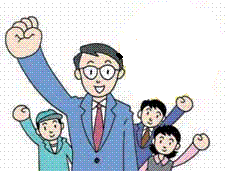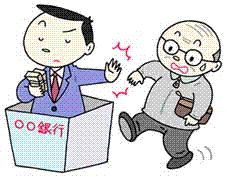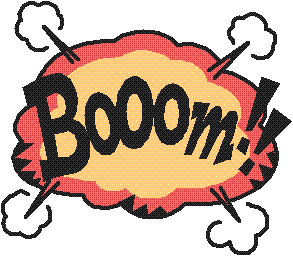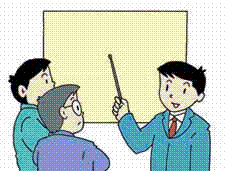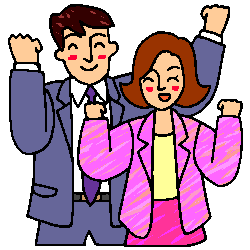★★★ リストラ・工場閉鎖に抗し、労働組合を結成し、団結の力で前進的解決
〜不動産仮差押え命令を得て、退職金確保 ★★★
1 東京の下町に本社のあるA化学工業株式会社では、
前社長を追い出した創業者一族は、
創業者の二代目を新社長に押し立てつつ、
顧問弁護士と顧問税理士を先頭に、
人員整理案を練っていたのである。
2 昨年3月になって、突然、会社は、
B工場を4月に、C工場を6月に廃止し、採算部門のみを中部地方のD工場に集中し、
その余の部門は、東南アジアの関連子会社と外注でまかない、
余剰人員約50名を整理解雇するというリストラ案を発表した。
労働組合もないうえ、本社事務所と三工場に別れていて、
正社員とパート従業員の意思疎通も十分ではないという悪条件のなかで、
突然の解雇という危機に直面した従業員らは、
代表を選出し、退職条件の向上を求めて慣れない交渉を始めたが、
社長や顧問弁護士は正規の退職金すら完全に払えるかどうかわからない
という態度をとり続けた。
3 B工場の閉鎖とB工場従業員全員の解雇が強行されたあとの昨年4月、
困り果てたC工場の従業員代表のKさんを中心に、
C工場のパート従業員も含む8割の従業員が
たんぽぽ法律事務所に交渉を依頼した。
Kさんたちの要求は、
整理解雇されることを前提に、
せめて正規の退職金は100%を確保をした上で、その上積みと、
退職金規程上は退職金の権利のない勤続3年未満の正社員やパート従業員
への一定の「退職手当て」を求めたいというものであった。
しかし、そもそも、
C工場の閉鎖や整理解雇が真にやむを得ないものかどうかについて、
会社側の誠実な説明は全くなく、
抽象的に経営の危機を訴えるだけで、
経営陣の内紛や経営責任に対する真摯な反省を欠き、
経営陣や創業者一族が自らの痛みを伴うことなく、
従業員にのみ犠牲を強いる再建策(C工場閉鎖と整理解雇)は、
元来、受け入れ難いものである。
代理人である私たち弁護士は、直ちに、
C工場の閉鎖反対・人員整理案の撤回を求めて、交渉を始めた。
4 交渉の過程で、
会社側は、
初めて、財務諸表なども示して、その経営危機の実情を明らかにした上で、
C工場を閉鎖後その跡地を売却し、
銀行などへの負債の返済に充てると共に、業員への退職金不足分に充て、
なんとか解雇従業員への規定上の退職金を100%支払うというに至った。
しかし、退職金の上積み分への回答は渋く、
目に見える十分な成果が獲得できないまま推移していた5月に至り、
直接閉鎖の対象とはなっていなかったD工場の従業員の約半数からも
ここにおいてすなわち、
D工場とC工場の従業員が手を繋いで
C工場閉鎖反対・整理解雇反対の闘いに立ち上がったのである。
D工場のC工場の闘いへの連帯は、
整理解雇の波がD工場に及びかねないことと
今回の工場閉鎖がD工場の労働条件の悪化を招くこと必至という
D工場の I さんを中心に闘いを広げ、会社側の姿勢を正すのに役立った。
更に、両工場の連帯は、
両工場の従業員中私たちに依頼した従業員全員(パート従業員を含む)で
A化学工業労働組合を結成するに至った。
弁護士を代理人としての個人としての交渉から、
労働組合の団結の力を基礎にした交渉へと発展を遂げたのである。
、
5 結局、会社の経営状況が、
新旧経営陣の責任に属する内紛及びバブル崩壊後の景気の悪化の反映などにより、
今回のC工場の閉鎖売却や一定数の整理解雇なくしては、
7・8月にも不渡り倒産が必至という財務状況が明らかにされたことなどから、
工場閉鎖は受け入れざるを得ないとの判断に至ったものの、
両工場の連帯した闘いによって6月には、
会社に退職金の一定の上積みと、
退職金規程上当然には請求権のない3年未満の正社員やパート従業員への
一定の退職手当金の支払いを約束させたのである。
ところが、その後7月中旬に至り、 メインバンクであるS銀行が、
自己の債権回収にのみ熱心で、
会社への支援を打ち切るらしいとの情報や、
C工場敷地の売却処分にあたって
退職金などの従業員への支払いを優先する
と言明してきた不動産譲渡税につき、
創業者一族の個人的利益(第二次納税義務者としての役員の個人責任回避)
を優先して納税資金をプールしようとする動きなどが表面化した。
6 やむなく、労働組合に結集した従業員の大多数は、
自己の退職金などの債権を保全するために、
会社側が売却しようとしていたC工場敷地につき、
東京地方裁判所に不動産の仮差押を申し立て、
7月19日付けで、仮差押決定を得たのである。
尚、この仮差押申立にあたっては、
保証金準備の困難やこの仮差押決定が、
会社の倒産(破産申請により上積み退職金などの成果がなくなるだけでなく、
資産状況によっては規定上の退職金すら100%の確保が困難になる恐れがあった)
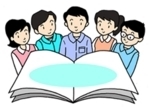
仮に、C工場の閉鎖売却・人員整理による会社再建計画がスタートしたとしても、
そのD工場に集中した再建策が必ず成功するという保証はなかった。
−やめるも地獄・残るも地獄−
結局、会社から整理解雇の通告を受けていた者のみならず、
D工場に残り、当面再建に協力する従業員も、一旦、退職の上、
組合員全員に対し規定の退職金100%を、
また退職金規定上は当然には請求権のない
3年未満の正社員やパート従業員への一定の退職手当金の各支払いを、
約束させることができたのである。
更に、労働組合へのまとまった金額の解決金や
有給休暇分の退職に当たっての買取りなど
も認めさせた。
8 右協定後も、9月30日の敷地売買契約の成立・実行までに、
会社の資金繰りがもつのかどうかという危機などを乗り越え、
右売買契約時に、仮差押の取下げと引き替えに約束の退職金などの大部分を受け取り、
程なく、協定書で約束された全額の支払いを受けることができた。
最初にたんぽぽ事務所を訪れたC工場のKさん
(彼自身は勤続3年未満の正社員で、
多額の退職金がかかっている立場ではないにもかかわらず、
パートさんを含む全員のために率先して献身的に行動した。
労働組合の書記長を務め、今回の人員整理で退職。) 、
唯一の労働組合経験者でD工場のまとめ役として、
遠方から何度もたんぽぽ事務所に足を運んでくれた労働組合副委員長のIさん、
若手で人望があり労働組合委員長に担ぎ上げられ、苦労しながらも成長したYさん