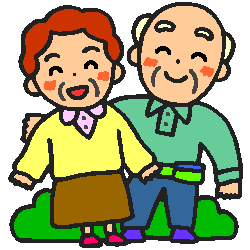★★ 妻の収入につき形式的判断を退け、実態を判断 ― 東京地裁判決 ― ★★
1 関東近県在住の中小企業(機械部品加工業)の社長の妻(65歳、監査役)が、

夫の死亡(1994年)後に、
社会保険庁長官を相手に、
遺族厚生年金不支給処分の取消を求めた訴訟で、
昨年11月5日、
東京地裁(藤山雅行裁判長)は、妻の訴えを認め、
不支給処分を取消した。
2 妻は会社の監査役として、 夫死亡の前年に
厚生大臣が定める当時の受給の基準(前年収入が年額600万円未満)
を上回る690万円の名目上の収入があったところ、
地元の社会保険事務所長はその収入を根拠に、
夫の死亡当時「死亡した者によって生計を維持したものとは認められない」として、
遺族厚生年金の不支給を裁定した。
審査請求等の棄却を経て、それを不服とする妻からの依頼で、
2000年7月に東京地裁に提訴した。
3 厚生年金保険法で、
遺族厚生年金を受給できる遺族とは、
「被保険者…の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」(法59条1項)と定められ、
本件当時の施行令は、
「法59条1項に規定する被保険者…の死亡の当時
その者によって生計を維持していた配偶者(ら)は、
当該被保険者…の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって
厚生大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者
その他これに準ずる者」
と規定されていた。
そして本件当時の厚生大臣の定める「生計維持」の基準金額は
通達で年600万円と定められていた。
又、その解釈を定めた別の通達で、
「前年の収入が年額600万円未満である」者も、
「生計維持」要件の収入基準をクリアするとされた。
4 本件では、妻はワンマン社長(夫)の経営する同族会社の監査役
として登記され、
役員報酬名目で夫の死亡前年には、
妻名義の口座に年690万円の振り込みを会社より受けており、
形式的には、通達による収入基準に合致していなかった。
しかし、本判決は、
会社の経営実態及び妻の勤務実態を詳細に主張立証した原告の主張を容れ、

妻は経理事務の手伝いをしていたのみで、
妻の担当業務は、
裁量の余地のない「従業員の給与・賞与計算…等の雑務に過ぎず、
…他の従業員により代替可能な簡単な事務処理」であったとし、
妻に支払われていた690万円の報酬につき、
「原告の労務の提供の対価として相当と認められる額を超えて決定され、
支払われていた」
と評価した。
更に、夫が妻を名目上監査役に就任させて高額の報酬を支払っていたのは、
身近な親族を役員に就任させることで会社運営の円滑化を図ること等
を意図した「一種の便法による」ものとした上、
原告の前年の「報酬690万円のうち、
原告の実際の労務の提供に対する対価と認められる額を超える部分は、
(夫による)経営権の掌握に由来する収入」であり、
妻が夫の「存在なくして独立に得ることのできた収入であるとは認められない」
とした。]
そして、判決は、
当時の妻の業務態様・勤務態様に照らせば、
妻の「労務の提供と対価性を有すると認められる収入額は、
同規模の会社従業員の収入額との比較において、
600万円に達するとは到底認められず」、
年間300万円程度を上回るものではないとした上、
「原告(妻)の(夫)死亡前年の収入のうち、
自らの労働の対価と実質的に認められる額は600万円に達していない」
と判断した。
判決は、右判断に基づき、
「本件の場合には、
原告(妻)の収入が形式的にみて厚生大臣の定める額を上回っていること
をもって法59条1項の要件を満たさないものとすることは、
…行政解釈又は解釈基準が同条の趣旨に反するものといわざるを得ず、
夫の存在があってはじめて基準以上の収入を得られたことに照らして、
原告(妻)は、被保険者である(夫)によって生計を維持していたもの
と認めるのが相当である。」
と結論づけた。
結局、
基準を形式的に適用し不支給処分を行った社会保険庁長官の判断は違法として、
不支給処分を取消した。
5 社会保険事務所の窓口では、
遺族厚生年金の相談に訪れた遺族に対し、前年の収入を尋ね、
前述の基準(現在は850万円)以上の年収のあった遺族に対しては、
基準を超えており遺族年金は受けられない旨回答し、
裁定請求書の用紙すら交付しない取扱いをしているのが実情である。
本判決は、
「生計維持」要件につき、
前述の通達の認定基準の形式的解釈を排し、
実態に則して柔軟に解釈して妻を救済した点で貴重であり、
実務の形式的な運用の改善を迫るものとなった。