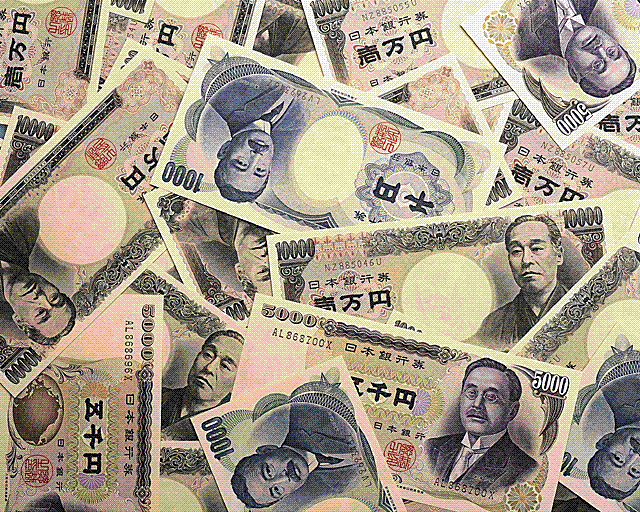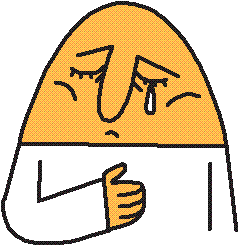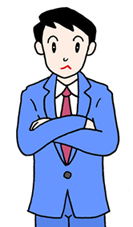今、内閣の司法制度改革推進本部で、司法制度を大きくかえる検討が、
多方面で進められ、順次、立法化されています。
昨年11月には、法科大学院(ロースクール)創設関連法が成立し、
金持ちしか法曹になれぬ危険が現実化しつつあります。
その外にも、
弁護士報酬の敗訴者負担、仲裁制度の拡充、裁判員制度の導入等を、
「司法改革」の名のもとに推進する動きが急ですが、
いずれも、国民の裁判を受ける権利や被告人の人権を制約しかねない危険があり、
国民の監視の目が重要となっています。
1 「弁護士報酬の敗訴者負担制度」
「弁護士報酬の敗訴者負担」が導入されれば、国民の裁判を受ける権利が制約され、
市民が裁判を利用しにくくなります。
そもそも裁判になるというのは、原被告双方にそれなりの言い分があってのことです。
一般市民の起こす裁判で、
提訴前から必ず原告が勝てると確信を持てるような事件は余りありません。
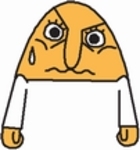
そのために、「敗訴者負担」になれば、
負けた時の相手方の弁護士費用の負担が心配で、
裁判に訴えることをあきらめたり、
訴えられても争うことをあきらめて不本位な和解での解決を
押しつけられることになりかねません。
とりわけ、消費者事件、労働事件、医療過誤事件、
公害・環境事件、行政事件などでは、
市民の側が勝訴することは容易なことではありません。
また、基地訴訟、靖国訴訟その他の憲法訴訟、
行政の無駄遣いを追及する住民訴訟等々も、
勝訴の見通しなど提訴時に確信できるものではありません。
相手方の弁護士費用まで「敗訴者負担」となれば、
薬害エイズやハンセン病の各被害者が救済を求めて立ち上がったり、
市民が裁判を通じて憲法の厳格な適用を求めたり、
社会の改善を図るための努力をすることが、極めて困難になります。
「敗訴者負担」の推進者は、
現状では勝訴しても弁護士報酬分の権利が目減りすると称し
その勝訴者の弁護士費用を敗訴者に負担させる方が
公平で司法へのアクセスをしやすくすると論じます。
潤沢な資金をもつ大企業や国などにとっては、
相手方の弁護士報酬の負担も平気の平左でしょう。
しかし、一般市民や中小企業家にとっては、
負けたときに相手方の弁護士費用まで払わされると聞けば、
裁判で争うことは断念せざるを得ません。
一般市民とりわけ社会的弱者にとって、
「敗訴者負担」は、裁判で争う権利を奪われるに等しいのです。
2 裁判外の紛争処理「仲裁」の拡充
裁判外の紛争処理手続きである「仲裁制度」の拡充も問題です。
元々企業間の紛争処理を念頭に論じられていたものが、
消費者や労働者等と企業との間での「紛争を仲裁で解決する」
との事前合意も有効とし、
労働者、消費者、その他の契約当事者が裁判に訴える権利を奪う
という大変危険な代物に化けかねないのです。
これは、「敗訴者負担」と並んで、
裁判の数を抑制し、裁判件数を減らすことを目的としもので、
反対の声を集中しましょう。
3 刑事裁判への「裁判員」制度の導入
一定の刑事裁判へ被告人の選択権抜きで導入
が予定されている「裁判員」制度も、
その本質は、陪審制とは似て非なるもので、
被告人の人権擁護の制度とは言い難い制度となる危険が大です。
現行の刑事手続き改善の保障なく、 代用監獄や長期勾留を温存したままで、
「裁判員」(素人裁判員の人数をできるだけ抑制したいというのが最高裁などの意向)
によるスピード裁判を強制するというのでは、
被告人の人権擁護や誤判防止への配慮はないも同然です。
引き続き、監視の目を光らせなければなりません。
4 「司法改革」の歩む先に監視の目を!
国民に「より身近な司法を」とのスローガンにもかかわらず、
「司法改革」の歩き始めた道は、司法を国民から遠ざけ、
人権擁護や弱者の保護の視点に欠けるところが
多々見うけられるものとなっているのではないでしょうか。
その先に国民の最後の砦は存在しているのでしょうか。
「まやかしの司法改革」とならぬよう、
監視の目を強めつつ、
弁護士報酬の敗訴者負担その他の改悪には、みんなで反対しましょう。
【追記】
幸い、この「弁護士費用敗訴者負担制度」は、
市民団体、労働組合、法律家団体等の大きな反対運動の盛り上がりにより、
国民の強い反対の声を結集することができましたので、
阻止することが出来ました。
しかし、
すきあらばこの制度を導入したいという推進勢力の巻き返しがあり得ますので、
引き続いての警戒が必要です。