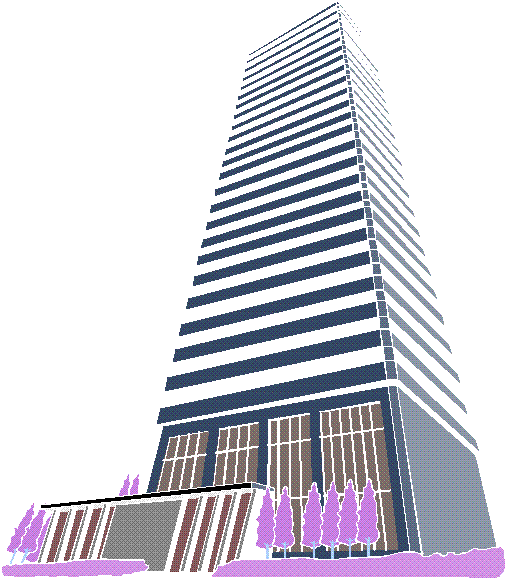★★ 1,200万円の和解金を勝ち取る ★★

1 私は、もうすぐ死にます。
私が死んだら、女房は途方に暮れるだろう。
女房に先生のお名前と連絡先を伝えておきます。力になってやって下さい。
女性の弁護士さんで良かった。
・・・病院を抜け出して医療法律相談に来たNさんは、
元倉弁護士にそう言い遺した。
その数ヶ月後、Nさんの妻が、
夫の死の報告をもってたんぽぽ法律事務所のドアを叩いた。
2 Nさんは、築地の青果市場で、青果の荷受け仕事に従事
する会社員であった。
Nさんは、煙草も吸わず、晩酌もビール1、2本程度、
体調が少しでも悪いときはその晩酌も控え、早めに就寝するなど、
自己の健康状態には十分慎重な注意を払っていた。
Nさんの勤務する会社では、
毎年秋に、加入している健康保険組合と会社が大部分の費用を負担して、
社員(組合員)の健康管理のために、「一日人間ドック」
を受けさせることにしていた。
Nさん(当時満53歳)も、会社入社後、
最初の人間ドック(第1回人間ドック)があった1993年10月以来、
毎年秋に、Uクリニックにて人間ドックを受診して健康管理に努めて来ていた。
3 Nさんの第1回人間ドックの検査結果は、
「胃炎の疑い」で精密検査を要するとするほかは、
「異常なし」というものであった。
右「胃炎の疑い」について、
Nさんは、早速、Uクリニックで胃カメラ(内視鏡)検査などの二次検査を受けたが、
結局、異常なしと診断された。
翌1994年10月に受診した第2回人間ドックの結果は、
全て「異常なし」というものであった。
さらに、1995年11月受診の第3回人間ドックの結果も、
全て「異常なし」ということであった。
4 ところが、Nさんは、1996年6月頃より、腹部の調子が悪く、
下痢が続き、物を食べると腹部が張る感じがするなど、
腹部に異常を感じたので、
1996年7月に、Uクリニックを受診し、
投薬を受け、尿と便の検査を受けたが、
特に「異常はない」との診断であった。
Nさんは、Uクリニックの薬を飲んでも腹部の異常が改善されなかったので、
J大学病院の関連クリニックで、胃カメラ等の胃の精密検査を受けた。
4 右検査の結果、
J大学病院消化器内科のM教授より、「胃癌の疑い」を示唆されたので、
Uクリニックの人間ドックのレントゲンフィルムなどを借り受け、

更に、J大学病院でM教授の診察を受けたところ、
1996年8月、確定的に「胃癌」との告知を受けた。
その際、M教授は、
Uクリニックでの第3回人間ドックのレントゲンフィルムを示しながら、
「残念ながら1年前に既に癌はできていました。
このときだったら、内視鏡で癌を取り除けたのに。」と説明した。
6 Nさんは、1996年8月、J大学病院に入院して、
更に精密検査を受けたが、
癌は第3回人間ドックの時より大きくなっているうえ、
既にリンパ節に転移していて手術はできず、抗癌剤の治療を受けることになった。
結局、Nさんは、1997年9月に、J大学病院に4度目の入院をするまで、
入退院を繰り返し抗癌剤治療を受けたが、副作用に苦しんだ挙句、
同年11月に胃癌により、満57歳の若き生涯を閉じるに至った。
7 本件は、「集団検診」より精密な検診が望まれる
はずの「人間ドック」での「癌の見逃し」が問題となる事案である。
Nさんは、J大学病院への入退院を繰り返している過程で、
元倉弁護士に、法律相談をした。
本人の希望もあって将来の裁判のために
Nさん本人の苦しみと悔しさを直接陳述書に作成したが、
Nさんは
「人間ドックでの癌の見落としで、57年の生涯なのか。」
と諦めきれぬ思いを語ってくれた。
8 Nさん死亡の2ヶ月余り後の1998年2月に、
カルテやレントゲンフィルム類の証拠保全手続きを行った後、
Nさんの妻は、1998年8月、
亡夫とご自身の苦しみと悔しい思いを晴らすべく、
東京地方裁判所に、
Uクリニックを相手取り、損害賠償請求の訴訟を提起した。
9 裁判で、原告は、
第2回人間ドックでのレントゲン写真にも
Nさんの胃癌発症の箇所(胃角小弯前庭部)に
「要精検」と判断すべき異常所見があったこと、
第3回人間ドックでのレントゲン写真でも
前記同箇所に
胃癌を強く疑って要精密検査と判断すべき異常所見があったこと
及び被告のその各見逃しの過失を主張した。
被告Uクリニック側は、
短期の人間ドックの検査は、スクリーニングのための検査であり、
結果的には異常所見が認められない場合が大多数であるとの前提のもとに
短時間に相当数の枚数の写真を読影しなければならないという特徴があり、
わずかな所見でもすべて精密検査に回すことになれば、
擬陽性の肥大化を招き、人間ドックの施行自体が困難になること、
原告の主張するレントゲンフィルムの異常所見は、
胃癌という結果がわかってからの「後知恵」と「先入観」に基づくものと争った。
被告のこの主張は、
「集団検診」を超えて、より高い費用を払ってでも「人間ドック」を受診する側の
「集団検診」のレベルを超えた慎重な検査及び判断を期待しているドック受診者
を裏切るものである。
10 東京地方裁判所の裁判では、
被告側から鑑定意見書が出されたが、
原告申請のJ大学病院M教授や
被告Uクリニックの担当医師の証人尋問が行われる直前に至り、

被告側から、和解による早期解決の打診があった。
結局、裁判所から、
被告に責任があることを前提とする損害賠償にふさわしい金額として、
金1,200万円が提示された。
原告も、
上訴審を含む今後予想される長期の裁判闘争を回避するメリットを認め、
右金額を受け入れ、本年4月に和解で解決したものである。
11 Nさんの妻も、
亡き夫の無念の幾ばくかを晴らすことができたのではないか、
闘ってよかった、苦労した甲斐があったと、
ほっと一息ついて、肩の荷を下ろした心境でいるということである。
(本件は元倉弁護士との共同事件です。)