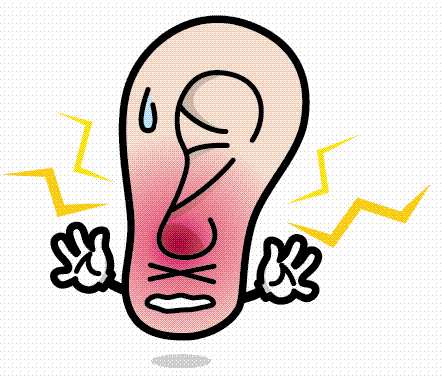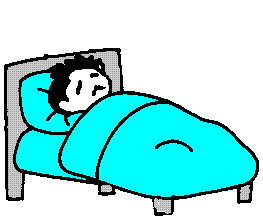★★ 聴神経腫瘍摘出手術後の管理不十分のため、脳に重篤な後遺症を残した男性
の医療過誤訴訟−1億5千万円の和解金を勝ち取る! ★★
1 Kさん(当時59歳)は93年秋、耳鳴りが続く
のが気になりO病院を受診。
検査の結果は、初期に発見できた小さな聴神経腫瘍(良性)。
術後2週間ぐらいで退院できる簡単な手術との説明を受け、
O病院脳神経外科に入院した。
2 Kさんに対する手術は、同年11月15日の午後行われた。
開頭の上、小脳のそばの聴神経から腫瘍を摘出するもので、
慎重な手技を要するものの、
一般の脳神経外科医にとっては、特別困難なものではなかった。
Kさんは、手術後一旦麻酔からさめた。しかし、
術後24時間経過した同月16日の夜8時ころから、
傾眠傾向等意識レベルの低下が見られ始めた。
手術の翌々日(同月17日)の早朝には
意識を失う等、重篤な脳障害(急性水頭症)を発症した。
緊急に、水頭症の手術(脳室ドレナージ術)が施行された。
意識は徐々に回復したものの、脳幹部に損傷が残っており、
身体障害者手帳一級に該当する重篤な後遺症を残し、
日常生活はほぼ全介助を要する状態となった。
3 Kさんと妻Nさんは、証拠保全手続きでカルテを押さえた後、
97年5月、O病院とH執刀医(某医科大学助教授)及びS担当医を相手取り、
東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。
本裁判では、
① 手術に際しての手技ミスの有無、
② 術後の患者管理のミスの有無、
③ ②に関連して手術の翌日(11月16日)朝に撮影した頭部CT写真の読影ミスの有無
などが、主な争点として争われた。
4 争点①について、
Kさん側は、
手術に際し、脳べら小脳若しくは小脳付近の細い静脈を圧迫・損傷し、
脳挫傷若しくは微量の出血をもたらしたと主張した。
しかし、H執刀医やS担当医らは、
手術を記録したビデオテープ上も術中にトラブルもなかったうえ、
出血の有無も確認していると反論した。
5 S医師は、手術後、一旦、Kさんの意識が回復した上、
手術翌朝(11月16日)撮影の頭部CT画像に異常がなかったと判断し、
午前の回診以降は、Kさんを診察することなく帰宅した。
担当看護婦らも、
11月16日の夜8時に傾眠傾向(意識レベルの軽度の低下)
にあることを看護記録に記載しながら、
特に担当医や宿直の医師に報告・相談することのないまま推移し、
手術翌々日(11月17日)の早朝6時頃に、Kさんの容態の急変に気づくまで、
何らの適切な措置をとらなかった。
この点が、Kさん側の主張する争点②についての事実である。
病院・医師側は、患者管理のミスを否定し、
急性水頭症の原因として、当初は原因不明を、
裁判の途中からは、上大静脈症候群なる稀な病気が発症したと主張し、
自らの責任を否定した。
6 しかし、手術翌朝(11月16日)撮影の頭部CT画像には、
手術部位近傍に、出血性の脳挫傷を疑い得る白っぽい異常画像があった。
又、同じ機会に撮影した3つの連続画像には、
脳幹と中脳に近い本件手術部位の近傍に、 凸レンズ状の白っぽく見える部分が写っており、
明らかな血腫を示す異常画像
(少なくとも異常を疑い適切な精密検査やより慎重な経過観察を要する画像)であった。

この点については、
裁判の終盤で、原告ら代理人が、
脳神経外科の協力医T氏に巡り会い、
T氏の鑑定意見書及び同氏の法廷での証言で、
原告側の主張を裏付けることができた。
7 提訴以来4年7ヵ月の審理
(人証調べとして、被告のS担当医、H執刀医、原告の妻の尋問の後、
協力医T氏の証人尋問を行った。)を経て、
01年12月に結審したが、
裁判所の積極的な和解勧告(原告勝訴を前提とするものであった。)に基づき、
和解交渉を続け、
本年4月、被告らがKさん及び妻Nさんに、
総額1億5千万円の解決金を支払うことで和解が成立した次第である。
実に、提訴以来約5年での解決であった。
なお、Kさんは、訴訟中もO病院に入院したままであったが、
和解解決を機に、介護の可能な施設に転院することになっている。
闘ってよかったとしみじみ語る妻Nさんの目には、きらりと光るものがあった。