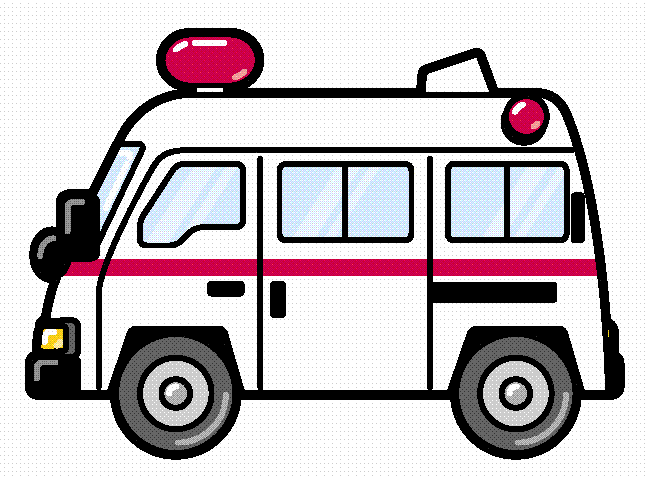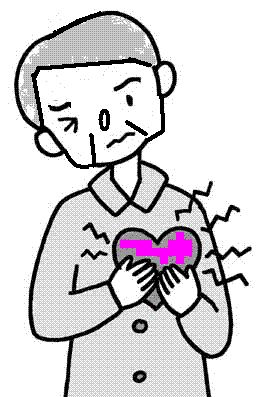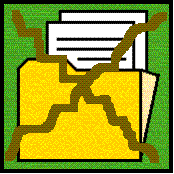★★ 救急搬送された心筋梗塞の患者に適切な治療を行わなかったために死亡させた
病院から和解金7,800万円を獲得 ―東京地方裁判所で和解― ★★
1 関東近郊に住むAさんの夫(54歳)は、90年12月1日(土)夜、仕事先で胸痛を訴えて倒れ、救急車で運ばれた。
かけつけたAさんは、診察した当直医から、
「軽い狭心症で念のため入院してもらうが明日には退院できるでしょう。」
と言われて安心し、夜中過ぎには後を義弟に託して帰宅。
Aさんは、同室患者の付添人から、容態急変を知らせに行ったが、
ナースステーションに誰もいなくて連絡が取れずかわいそうだったと聞かされた。
2 夫の急逝後、Aさんはショックのあまり体調を崩し、
夫の急死に納得できないまま行動することなく5年近くを過ごした。
5年のカルテ保存期間満了の数ヶ月前に
やっと法律相談に「たんぽぽ」を訪れたAさんに、
病院への責任追及の前提として、カルテ類の証拠保全をお勧めした。
3 大急ぎで準備をし、95年10月20日、地元の裁判所に証拠保全を申し立てた。
裁判所の決定で、保存期間ぎりぎりの11月30日、
カルテ類の検証のために病院を訪れた。
しかし、本来ある筈のカルテ類が行方不明として出てこなかった。
辛うじて提出されたのは、診療報酬明細書(レセプト)、
入退院台帳等の附随資料のみであった。
4 証拠保全で十分な資料が得られなかったが、
レセプト記載の処置や投薬を検討する一方、
Aさんや入院当夜付き添った義弟などの記憶を喚起し、
容態急変に至る経過や急変後の病院の措置などを検討した。
結局、どうしても、夫の突然の死亡に納得のできなかったAさんは、
97年3月6日、病院側と管轄合意の上、東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起した。
5 裁判では、当初、レセプトや当事者の記憶に基づき、双方の主張立証が為された。
事実の争点は、
①患者の入院は一般病室か、当初よりICUだったか、
②心電図モニターで入院直後から監視していたか、
③容態急変にすぐ気づいたか等であった。
原告側は、
「胸痛を訴え救急車で運ばれた心筋梗塞の患者を、狭心症と即断し、
心筋梗塞に必要な治療をしなかった」病院の落ち度を追及した。
6 裁判では、カルテがない前提で、
被告病院の当直医、病院で待機していた患者の義弟らの証人尋問、Aさんの原告本人尋問を行い、結審間際となった。

ところが、01年3月、
被告から別の棚から見つかったとしてカルテ類が突然提出された。
そのカルテ等によれば、前記争点につき、Aさんの体験とは違い、
①当初からICUに入院し、
②心電図モニターで監視していた旨の記載があり、
③容態急変にすぐ気づき、医師が駆けつけたことになっていた。
結審間際も提出されたカルテ類は、病院側に都合良く改竄された疑いが強く、
原告側は、カルテ改竄の主張をしつつも、
仮にカルテどおりであったと仮定した場合の過失も主張した。

7 原告側は、協力医の鑑定意見書を提出し、
カルテ記載どおりだとしても、
①心筋梗塞と診断すべきを狭心症と即断し、
血栓溶解療法等の心筋梗塞の初期段階でやるべき治療をしていない、
②投与すべきではない薬(アミサリン)を繰り返し投与した、
③点滴量が過量であるなどの病院側の過失を指摘。
結局、看護婦や協力医の証人尋問を経て、
04年11月22日に結審、裁判所が和解を勧告した。
8 和解の場で、裁判所は、カルテ改竄との原告主張までは認めなかったものの、
「心筋梗塞に必要な治療をしなかった点で被告病院に全面的な責任がある」
ということを前提に、
「カルテの提出が遅れて原告の訴訟進行に遅れを生じさせた」
点も損害として加味した和解案を提示した。
被告側の抵抗はあったものの、
05年5月11日、被告病院が原告(Aさん家族)に、
和解金7,800万円を支払うことで和解が成立した。
実に、
本件医療事故発生から14年5ヶ月余、提訴以来約8年2ヶ月余での解決であった。
時間はかかったが、諦めないでよかった
・・・亡き夫の無念を晴らせ、Aさんは満足気であった。