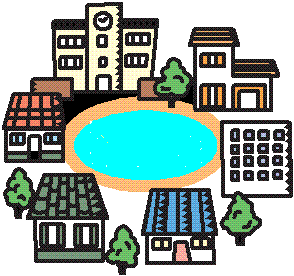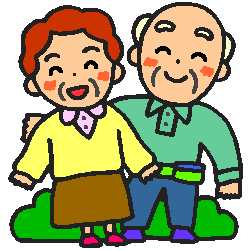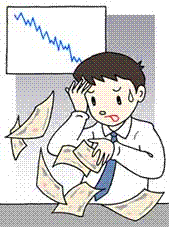その不安に付け込んだのが、B銀行の担当者Cである。
「一銭も手元から出す必要がない、
この上ない相続税対策である」として、
手持ち不動産を担保に銀行から巨額の融資を受けて、
高額の保険料・ 登記費用等を支払い変額保険に加入する
―という相続税対策のプランを勧誘した。
Cは、自ら紹介した公認会計士Dに説明資料を作らせ、
D公認会計士や知り合いの保険ブローカーEと相談を重ねた上、
Aさんにこの相続税対策を採用しB銀行から融資を受けるよう強く働きかけ、
自らの銀行内における成績向上を期した。
ところが、変額保険は、保険料を株などで運用し、
その結果、最低保証があるとはいえ死亡保険金は変動し、
解約返戻金は、最低保証はなく上にも下にも動くので
支払い保険料をも下回り得る−という「リスク」を内包していた。
保険運用の結果のツケを、保険会社ではなく契約者に帰する
−これが変額保険の知られざる仕組みであった。
運用の良いときはハイリターンが期待できる代わりに、
運用が悪くなればそのツケは全て契約者が負担するというハイリスク商品であった。
3 更に、銀行融資により巨額保険料を支払うという相続税対策の場合、
銀行金利の負担がその「ハイリスク」を加速する。
時の経過とともに膨らむ金利の負担が、運用悪化の「リスク」に加わり、
契約者の負担する「リスク」は天井知らずとなるのである。
4 本件相続税対策の勧誘を受けたAさんは、おきまりのように、
この変額保険の「リスク」や変額保険を使った相続税対策の「リスク」につき、
素人に理解できるような説明は誰からも一切受けていない。
本件Aさんに対する勧誘は、
B銀行のC、公認会計士のD、保険ブローカーEの3者が適宜相談・打ち合わせの上、
Aさんのそれぞれに対する専門家としての信頼を上手に利用し、
役割を分担して為された。
負担のない安全な相続税対策と信じ込まされたAさん家族は、
総額17億円を超える保険料で、
死亡保険金合計額約52億円もの巨額の変額保険
(保険会社6社)に
B銀行などからの融資を受けて加入した。
なお、本件保険契約を締結した保険会社6社の担当者は、
Eの指示で、
変額保険や本件相続税対策についての説明を直接Aさんに一切しなかったし、
パンフレットなどの公式書類をAさんに渡してもいない。
5 「この上ない相続税対策ができた」と安心したAさん一家であった。
しかしながら、時は流れ、
本件のような融資一体型変額保険が多大の損害を出している
ことを聞き及ぶに至り愕然とする。
Aさん達には、結局、全保険の解約と銀行への返済を済ませると
5億数千万円の実損が残った。
6 この被害の回復を求めたAさん達に対して、
東京地方裁判所は、
その被害の2割の救済を必要と認め、
この春、公認会計士D、ブローカーE及び生命保険会社6社に対し、
合計約1億2千万円の支払いを命じた。
中心的役割を果たしたとAさんが主張したB銀行については、
保険成約に伴う生保各社からの手数料千数百万円を実質的にB銀行が取得した事実
を認定し「不明朗」と指摘したものの、
本件変額保険及び相続税対策の説明をしたのはD及びEであるとして、
責任を認めなかった。
Aさんは、
B銀行の責任問題
及びAさんが自ら公式パンフレットなどを求めようとしなかったことを過失として
損害の8割を減額された点などを不服として控訴し、
敗訴した被告も全員控訴した。
東京高等裁判所での控訴審はいよいよこれから始まるところである。引き続きご支援を。