だまされるものの責任〜(2017年1月1日)元倉
いつの間にか戦争が始まっていた。

戦争が始まってしまうと、
「八紘一宇」「進め一億火の玉」となった。
教科書はもちろん、教師が、教頭先生が、校長先生が、
みんな確信をもってそう教えた。
ご近所が、親戚が、職場の同僚が、まわりの人たちが、みんな目を光らせていた。
勤務先の上司が、上官が、みんなそう命令した。
新聞も雑誌もラジオも、大本営発表で毎日日本中の空気を熱く満たした。
当時振り返る国民の声の多くが、「だまされていた」調なのが気になる。
今ほどに国民の教育水準や政治意識は高くなく、
今ほどにメディアの種類・数等も豊富ではなく、
今ほどに国民の声を発する手段も機会もなかった。
しかし、国民の目、耳、口が塞がれていたから仕方ないと言えるだろうか。
ここ10年の我が国の急速な右傾化は、

周辺諸国のみならず欧米諸国も
不安と警戒感を強くしているところだが、
それに比べると
我が国の国民のかなりの部分は呑気にみえる。
後になって、
また「だまされていた」というのだろうか?
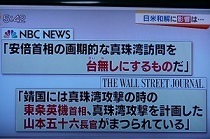
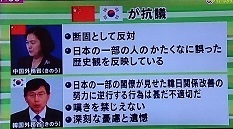
70年も前の1946年、
とある映画監督が「戦争責任者の問題」と題するエッセイを世に出していた。
敗戦の翌年、作者が46歳の若さで亡くなる直前の作品である。
震えが走る。
現代にも警鐘を打ち鳴らすこのエッセイの一部を紹介したい。
だまされたとさえいえば、
一切の責任から解放され、
無条件に正義派になれるように勘違いしている人は、
もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。
だまされるということ自体がすでに一つの悪である
だますものだけでは戦争は起こらない。
だますものとだまされるものとがそろわなければ戦争は起こらない
ということになると、
戦争の責任もまた(たとえ軽重の差はあるにしても)当然両方にある
だまされたものの罪は、
ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、
あんなにも造作なくだまされるほど
批判力を失い、
思考力を失い、
信念を失い、
家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになってしまっていた
国民全体の
文化的無気力、
無自覚、
無反省、
無責任などが
悪の本体なのである。
あのような専横と圧制を支配者にゆるした
国民の奴隷根性とも密接につながるものである。
奴隷状態を存続せしめた責任を
軍や警察や官僚にのみ負担させて、
彼らの跳梁を許した自分たちの罪を真剣に反省しなかったならば、
日本の国民というものは永久に救われるときはないだろう。
「だまされていた」といって平気でいられる国民なら、
おそらく今後も何度でもだまされるだろう。
いや、
現在でもすでに別のうそによってだまされ始めているにちがいないのである。
【青空文庫より抜粋
1946年4月28日伊丹万作/『映画春秋』創刊号(1946年8月)】

